はじめに
最近、会計士試験の勉強で感じることがあります。
それは「仕訳は切れるようになってきた。でも、なぜそうなるのか?という本質的な理解はまだ浅いかもしれない」ということ。
焦りはありません。
ただ、だからこそ今の自分の立ち位置や気づきを言語化し、記録しておこうと思いました。
財務会計|仕訳はできる。でもその“意味”は?
収益認識:構造が見えてきた
履行義務ベースで収益を認識するという考え方には、ようやく慣れてきました。
リベートや返品権付き販売など、可変対価の処理も一通り演習を重ね、手が動く感覚はあります。
「収益=価値の移転」という原則が、少しずつ馴染んできています。
成果連結・連結税効果:ここが今の“壁”
ここは今の自分にとって、まだ“うろ覚え”に近い論点です。
- 成果連結でなぜ内部利益を消去するのか
- 一時差異がなぜ生じ、連結税効果の対象になるのか
仕訳自体はこなせます。
ただ、なぜその処理が必要なのかを明確に言語化できない。
この段階から、“構造理解→再整理→自分の言葉にする”工程に入っていきます。
管理会計|細かい構造を押さえることの重要性
労務費:直接作業時間と賃率
直接作業時間には「加工時間」と「段取時間」の両方が含まれます。
また、残業手当や危険手当を含めた賃率の調整も必要。
単純な「人件費÷時間」では見落としが生じやすく、試験でも狙われがちなポイントです。
意思決定会計:キャッシュフローと税のリアリティ
投資の意思決定問題では、「損益」ではなくキャッシュフロー(CF)で判断。
今日の理解ポイント
- タックスシールド(減価償却費 × 税率)は意思決定に重要な要素
- 除却損や売却損益も、税効果を加味した“実質CF”で考えるべき
例:除却損5万円 ×(1−税率30%)=実質CF ▲35,000円
損益→資金の変換に慣れる必要を感じました。
今の自分に、こう言いたい
仕訳が切れるのは、第一段階を突破した証です。
でも、そこに「なぜ」「どうして」が加わったとき、理解は“自分のもの”になります。
まだ曖昧さはあります。
でも、その曖昧さを自覚できることこそ、前進の証です。
これからの学習方針
- 成果連結・連結税効果を図解+言語化で整理
- 労務費の計算パターンを“理解ベース”で再構築
- 意思決定会計では損益→CFへの変換練習を積む
終わりに:仕訳の向こう側へ
会計士試験は、知識量だけでなく「構造理解」と「実務感覚」を問う試験です。
焦らず、でも確実に、深く理解して前に進んでいきます。
今の自分はまだ、完成形ではない。
でも、「理解したい」と思い続ける限り、きっと辿り着ける。
この記録が、未来の自分と、誰かの背中を押せる記事になりますように。

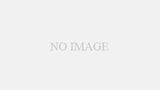
コメント